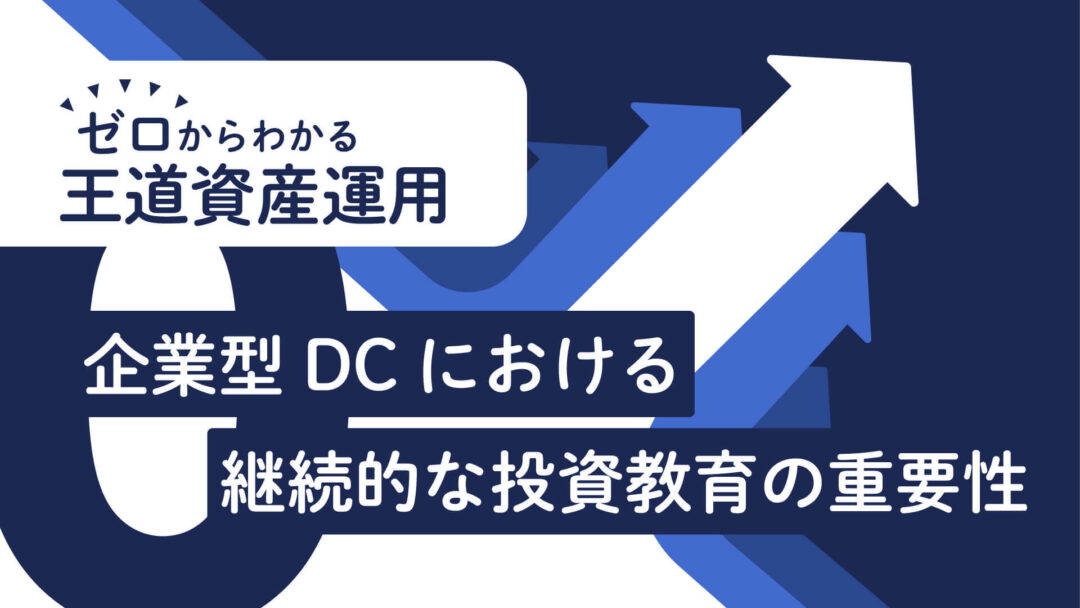
【努力義務】企業型確定拠出年金における継続的な投資教育の重要性
企業型確定拠出年金(企業型DC)は、公的年金を補う目的があるため、企業にとっても従業員にとっても税制面で優遇を受けられる制度となっており、年々実施する企業が増加しています。
この制度は、従業員自身が資産を運用していくのが特徴で、ひとりひとりの運用でそれによる将来の給付額が異なるため、適切な運用をおこなう必要があります。
そのため、企業は制度を導入して終わることなく、従業員に制度をしっかりと理解してもらい、適切に資産を運用できるように継続的にサポートする必要があるのです。
このように、企業が従業員に対して投資の教育をすることは、確定拠出年金法第22条の規定により、企業型確定拠出年金を実施している事業主の「努力義務」と定められています。
そこで今回は、従業員に対する企業型確定拠出年金の投資教育とポイントについて解説します。制度導入や運営にぜひお役立てください。
企業型確定拠出年金についての「投資教育」とは
企業型確定拠出年金(企業型DC)は、企業が毎月決まった掛金を拠出し、加入者となる従業員が自ら年金資産の運用をおこなう形の私的年金になります。
この制度の加入者は、企業が用意した投資信託・預金・保険等の運用商品から自分で選んで運用と管理をし、その運用結果に基づく資産を年金として将来受け取ることとなるため、ひとりひとりの運用の結果次第で将来の給付額が異なります。
そのため、従業員は資産運用をおこなうための情報や知識、そして給付金の受給時期等の制度に関する情報や知識も有していなければなりません。
そこで、従業員への制度の説明だけでなく、継続した投資教育をすることがとても重要となります。
投資教育とは、制度に加入する従業員に対し、企業が制度の仕組みと基礎知識・資産運用の知識・ライフプランニングに関する知識などの必要な情報を提供し、理解を深めてもらうためにおこなう教育です。
このように、企業から加入者などに対して投資教育をすることは以前より「配慮義務」とされていましたが、2022年10月1日施行の確定拠出年金法第22条の規定により、企業型確定拠出年金を実施している企業の「努力義務」と定められています。
この投資教育は、企業の義務となり、果たしていない場合は「企業側からの投資教育が実施されなかったために、適切な運用ができず、損害を被った」として従業員の退職後に訴訟を起こされるリスクもあるのです。
そのような事態を防ぐために、企業型確定拠出年金制度の導入後は、従業員にまかせきりにするのではなく、従業員それぞれが将来のために資産形成ができるようにサポートしていくことが必要といえます。
従業員のための投資教育のプログラムとは
実際に、従業員に対してどのように投資教育をおこなっていくのか、どのような投資教育のプログラムを組むのかを検討してみましょう。
たとえば、「どのように運用商品を選んだら良いのか?」「運用の収益はどこで、どのように確認するのか?」などといった基本的な疑問に応えるものから、投資の経験者であれば、よりレベルの高い内容の教育など、従業員それぞれに合わせたものが用意できると理想的です。
このような観点から、以下のような従業員に対しての投資教育のプログラムに入れるべき必要なポイントを抑えて、自社で行う場合にも、運営管理機関・企業年金連合会・投資教育の研修をおこなう団体などに外部委託する場合にも、ぜひお役立てください。
投資教育プログラムをおこなう際のポイントと注意点
投資教育プログラムをおこなう際に重要なことは、以下の通りです。
- 企業型確定拠出年金制度への理解が深まること
- 従業員自身のライフプランに適した運用ができること
- 従業員が制度における「運用の指図」の意味を理解すること
- 従業員が自分で資産配分をおこなえること
- 従業員が自分で運用による収益状況の把握ができること
上記のようなポイントを押さえて投資教育を実施することとなりますが、従業員により、投資への興味関心・知識・経験が異なることを念頭に置いて教育内容を準備できるとより好ましいです。
年代層で分ける
同じ企業に従事する従業員であっても、年代によって退職までの期間だけでなく、現在の状況や将来設計が異なり、それにより理想とする運用も異なるでしょう。
それぞれの世代に合わせた投資教育をおこなうことは、より従業員のニーズに応えるためにもぜひ取り入れてみてください。
投資の知識・経験に応じて
投資の知識や経験は、かなり個人差があると考えるようにしましょう。
企業型確定拠出年金制度は、すでに投資の経験があったり、知識が豊富にある人だけではなく、企業に従事する従業員全員が加入するものなので、投資に関して知識がなかったり、苦手意識を持っている人も、自分で適切に資金運用できることが大切です。
そして、投資教育は1回では終わらず、継続的におこなわれる必要があるため、回数が増すごとに従業員の知識も蓄えられていくような投資教育を目指していきましょう。
それでは、投資教育の段階について解説していきます。
投資教育は3段階でおこなう
先述したとおり、企業型確定拠出年金の加入者である従業員に対しての投資に関する教育は、導入時だけでなく導入後も継続しておこないます。
さらに、退職時に資格を喪失した従業員(加入していた人)に個人別管理資産の移換について説明することで、従業員の加入・運用・受給までをサポートすることが必要となります。
1.導入時(加入時)の教育
企業は、加入者である従業員が企業型確定拠出年金制度に加入後も、個々人のニーズに合った適切な運用の指図※をできるようにする必要があります。
「運用の指図」とは、自らが選んだ運用商品で、どのように資産を配分するのかを運営管理機関に提示することを指します。
そのためには、確定拠出年金制度における運用の指図の意味を理解し、具体的な資産の配分を自らおこなうことができるとともに、自ら運用による収益状況の把握ができることを目的として、必要な項目を中心に投資教育がおこなわれることが理想的です。
制度の概要を理解してもらう
まず最初に、企業型確定拠出年金制度の導入時または加入時には、制度の概要を理解してもらうことが大切です。
制度の内容を深く理解してもらうとともに、将来のライフプランを描いてもらい、そのための資産計画に興味や関心を持ってもらうことが大切です。
初心者にもわかりやすいように丁寧に説明する
従業員によっては、投資自体が初めてだったり、投資の知識や情報がない場合もあります。
企業型確定拠出年金は個々人で運用するため、それぞれにおける投資の知識や経験が運用結果に大きく影響することもあり、将来受け取る給付金が変動してしまうため、投資教育は非常に重要となります。
このように、投資に関する知識や経験の有無によって従業員の運用に差が出ないように、初心者にもわかりやすく、丁寧に解説して加入者となる全員に理解を深めてもらうことが大切です。
そのためには、運用シミュレーションを用いた説明や事例などを取り入れて解説していくのもおすすめです。
企業型確定拠出年金の導入または加入時の投資教育内容として、欠かせないポイントは以下の通りです。
【導入時(加入時)の投資教育の内容】
- 公的年金と私的年金など、年金制度全般の基礎知識
- 企業型確定拠出年金制度の概要
- 自社の福利厚生制度・退職金制度・企業型確定拠出年金制度
- ライフプランニングとそのための資産形成に関する考え方
- 資産運用に関する基礎知識〈運用におけるリスクとリターン・資産配分など〉
- 金融商品の仕組み・種類・特徴と選び方
- 制度加入に必要な手続きや手数料
- 受取時に関して
2.加入中の継続的な教育
企業型確定拠出年金は、従業員それぞれが自身で資産運用をしていく制度です。
資産運用に関しての知識や経験を問わずに、適切に運用できることが必要となることから、企業による継続的な投資教育は「配慮義務」から「努力義務」へと格上げされました。
そのため、導入時または加入時の投資教育だけで終わらせることなく、運用期間中は定期的に投資に関する知識や最新の情報を増やしていく継続的教育が必要となります。
積極的に運用してもらうために
企業型確定拠出年金制度の教育は、導入時または加入時だけでなく、導入後も継続しておこなうことで従業員の制度に対する理解を深めてもらいます。
しかし、投資やライフプランニングについて知識がなかったり、資産運用を深く理解できてない人は、積極的に運用することが難しかったり、適当に運用商品を選んでしまうかもしれません。しかし、上手に商品を見極めたり運用をしていかないと、原本割れしてしまうこともあり、せっかく将来に向けて資産形成をしているのに、勿体ないことになってしまいます。
このような事態を防ぐためには、従業員が投資の知識をしっかりと身に着けて、適切に運用することが大切となり、企業は企業型確定拠出年金を導入した後も、継続して制度や投資の知識を深める機会を提供していくことが必要となります。
また、場合によっては、企業型確定拠出年金の運用期間中に離職や転職をすることもあるかもしれません。このような場合でも、企業型確定拠出年金は資産を持ち運べることなど、制度についての様々な事例や説明をしていくことが従業員に寄り添ったサポートに繋がります。
従業員の制度理解を深める工夫
企業型確定拠出年金は、従業員が個人で中長期の資産形成をすることとなるため、従業員が自身のニーズにあった投資ができるよう、企業は知識向上や新しい情報を得られるようにサポートします。
たとえば、金融商品は運営管理機関によって異なるため、それぞれの種類や特徴などを理解してもらったり、運用のコツや資産配分などは、運用のシミュレーションを用いて解説したりするのもおすすめです。
そして、その運用している資産が、将来受け取る給付金となり、老後の生活を支えるということを都度認識してもらうことで、個々人が長期的に責任を持って運用していけることとなるでしょう。
このように、従業員が企業における制度と設計をふまえ、それぞれの金融商品の特徴を考慮したうえで商品を選択し、運用するときはリスクをできるだけ抑え、将来のためにリターンを得られるように教育をすすめてください。
教育の方法や頻度は?
投資教育は「努力義務」ですが、実施する頻度や時期に関しては定められていないので、それぞれの企業が設定します。
多くの企業では、投資教育を年1回以上おこなうことが多く、自社で独自の教育をしたり、企業内部で投資教育ができない場合は、運営管理機関・企業年金連合会・投資教育の研修をおこなう団体などに外部委託することもできます。
投資教育の実施を運営管理機関等の第三者機関に委託するときの注意点
企業が内部で投資教育をするのが難しい場合、その実施を第三者機関に委託することが可能です。
しかし、企業の投資教育の実施義務がなくなったわけではなく、実施の主体は企業であることを忘れてはいけません。
法令解釈通知(平成13年8月21日厚生労働省年金局長通知)では、投資教育を委託する場合の注意点を以下のように述べています。
「事業主が確定拠出年金運営管理機関又は企業年金連合会に投資教育を委託する場合においては、当該事業主は、投資教育の内容・方法、実施後の運用の実態、問題点等、投資教育の実施状況を把握するよう努めること。また、加入者等への資料等の配布、就業時間中における説明会の実施、説明会の会場の用意等、できる限り協力することが望ましい。加入後の投資教育についても、その重要性に鑑み、できる限り多くの加入者等に参加、利用の機会が確保されることが望ましい。」
厚生労働省ホームページ「確定拠出年金制度について」より
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12500000-Nenkinkyoku/0000192435.pdf
また、厚生労働省のホームページでは、委託先例・企業年金連合会(継続投資教育事業)のリンク・投資教育に関するチラシなどが紹介されていますので、これらも活用して投資の教育を進めていきましょう。
【委託先例】
運営管理機関
運営管理機関登録業者一覧
※すべての運営管理機関が投資教育の委託を受けているわけではありませんので、詳細は各運営管理機関にお問い合わせください。
企業年金連合会(継続投資教育事業)
その他の投資教育を受託している会社各社へお問い合わせください。
厚生労働省
【導入後の投資教の内容】
- 企業型確定拠出年金制度知識を継続してアップデート
- 資産運用に関する基礎知識〈運用のコツや資産配分など〉
- 企業からの毎月の拠出・運用・給付の各段階における税制措置
- 金融商品の仕組み・種類・特徴と選び方
- 自社における制度と設計の理解を深める
- 運用商品の変更(変更の方法とタイミングなど)
3.退職に際して資格を喪失した加入者に対しての説明
企業型確定拠出年金は、積み立てた資産を原則60歳まで引き出すことができません。
また、加入者である従業員は、60歳までに離職または退職をした場合、離職または退職後6か月以内に、他の確定拠出年金に資産を移換する必要があります。
この場合、移換先として企業型確定拠出年金・確定給付企業年金・iDeCoなどがあげられますが、企業型確定拠出年金と確定給付企業年金に関しては、転職先となる会社で該当する企業年金を実施している場合に限られます。
このように、企業は従業員が加入者の資格を喪失した場合、もしくは企業型年金が終了した場合は、スムーズにその資産を持ち運べるよう、個人別管理資産の移換に関する事項について説明し、必要な手続きをおこなえるように周知する必要があります。
従業員のための投資教育は、専門家に相談・委託も検討して
企業型確定拠出年金を導入・運営する際は、従業員への投資教育が必ず必要となります。
そして、この教育は導入時(加入時)だけでなく、導入後にも継続して定期的におこなわれ、加入資格を失ったときにもおこなわれます。
このように、企業として投資の教育をすることは「努力義務」とされており、従業員が適切に資産運用し、将来の生活に備えることができるようにサポートすることはとても重要です。
企業型確定拠出年金の投資教育が企業内で難しい場合は、運営管理機関や企業年金連合会などに委託することもできます。
第三者機関となる外部に委託する場合も、説明会の実施や就業時間への配慮などの協力を惜しまず、企業が実施主体であることを忘れずに、積極的に関わっていくようにしましょう。


