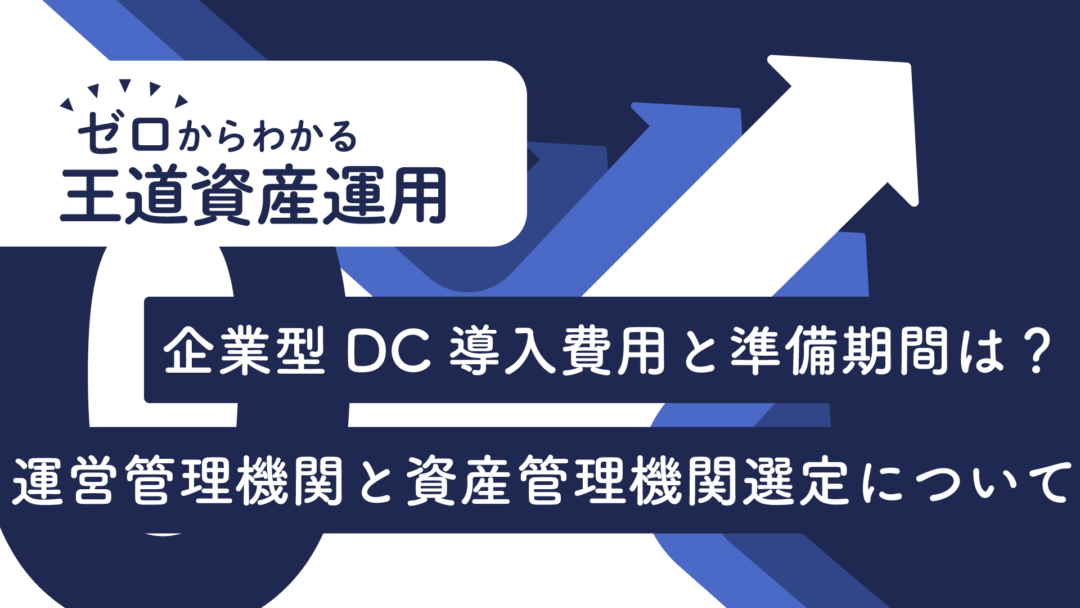
企業型確定拠出年金の導入費用と準備期間は?運営管理機関と資産管理機関選定について
「企業型確定拠出年金」は、企業が用意する福利厚生制度として人気を集めています。
この制度は、中小企業はもちろん、一人法人(ひとり社長)でも導入できたり、企業も従業員も税制優遇を受けられるなど、大変魅力的な制度です。
ただし、この制度を導入するには、時間と費用がかかります。
また、制度を安定的に運営するための担当者の配置や管理体制を整備、従業員への投資教育の必要となるため、事前準備が必要です。
この記事では、企業が企業型確定拠出年金制度を導入する場合にかかる費用とスケジュールに焦点を当てて解説していきます
制度導入を検討している企業の経営者や制度のご担当者様は、ぜひご参考ください。
福利厚生として注目を集めている「企業型確定拠出年金」とは
企業型確定拠出年金は、企業が掛金を拠出し、加入者となる従業員個人が拠出金を運用し、将来のための資産を中長期かけて形成する仕組みの企業年金制度です。
アメリカの確定拠出年金制度の「401k」をモデルとして作られた制度で、「確定拠出年金(Defined Contribution Plan)」を略して「企業型DC」とも呼ばれています。
従来の企業年金のリスク
従来の企業年金制度は、従業員の将来受け取る給付額が決まっている「確定給付型」が主流で、その年金資産の原資の運用や足りなかったときの補填は、企業側が責任を負うことになります。
企業としては、長期間にわたり事業に貢献してくれた従業員の将来のために必要な給付額を準備したいところではありますが、日本の経済状況などの影響で、確定給付型の企業年金の準備が困難になったり、予想以上に負担を負うことで経営するための財務を圧迫されてしまう企業も増えてきました。
とはいえ、退職金をなくしたり乏しい場合は、従業員の将来の生活が脅かされることになってしまうかもしれませんし、約束した金額を用意できない場合は、企業としての信頼を失うこととなってしまいます。
同時に、企業負担を増やさないようにする必要があり、企業はこのすべてのリスクも回避しなければなりません。
企業型確定拠出年金のメリット
各企業における企業年金のリスク回避の方法として、アメリカの「401k」をモデルとした「確定拠出年金制度」が日本でも導入されました。
確定拠出年金には平成13年10月から開始された「企業型」と、翌年の平成14年1月から開始された「個人型」があります。
このうち、企業型となる企業型確定拠出年金には、給与の一部を現金で受け取るか、掛金として企業型確定拠出年金に拠出するかを従業員が選択できる「選択制DC」や、企業が拠出した掛金に加え、従業員が自己負担で追加拠出できる「マッチング拠出」もあり、企業ごとに拠出方法や拠出額を設定し、自由に制度を作ることができます。
さらに、今日に至るまで法改正も重ねられて、各種制度との併用が可能になったり、上限額が増えるなど、より利用しやすくなってきているといえるでしょう。
このように、企業型確定拠出年金制度は、企業にとっても従業員にとってもメリットがある制度として注目を集めており、導入する企業が年々増えてきています。
企業にとってのメリット
- 運用責任を負わない
- 企業が負担する拠出金は、全額損金計上できる
- 福利厚生の充実は、新規人材獲得や人材定着に繋がる
従業員にとってのメリット
- 通常の投資とは異なり、掛金に課税されない
- 運用益は非課税となる
- 受取時にも税制優遇が受けられる
デメリットも確認しておこう
企業型確定拠出年金の導入には多くのメリットが考えられると同時に、それに伴うデメリットも無視できません。
特に企業側においては、制度の導入が決定されてから実際に運用を開始するまでに、導入のための費用や準備期間が必要とされます。
まず、制度を適切に管理・運営するための担当者や管理体制を整える必要があることが考えられます。
そのために、制度を運営するための担当者や従業員への投資教育の担当者を用意する必要があり、時間とコストがかかるでしょう。
また、加入する従業員に対しては、ひとりひとりが自身の退職金プランを理解し、適切に運用できるように、企業は投資教育を提供する必要があります。
次に、制度の導入自体にも、初期費用と継続的な運用コストが発生します。
企業は導入に先立ち、詳細なコスト分析と長期的な財務計画を立てる必要があり、制度導入までのプロセスは、数カ月を要するのが一般的です。
急いで導入を進めてしまうと、設計に不備が生じるリスクが高まるため、注意しなくてはなりません。
したがって、企業型確定拠出年金の導入を検討している企業は、制度のメリットとデメリットを慎重に検討し、全体的なスケジュールと予算計画に基づいて導入計画を策定していきましょう。
企業型確定拠出年金制度導入には費用がかかる
企業型確定拠出年金は、企業にとっても多くのメリットがある制度であるため、導入したいと考える経営者や担当者は多いでしょう。
ただし、制度の導入には初期費用や手数料などのコストがかかることを忘れてはいけません。
企業型確定拠出年金制度を導入する場合には、事前に必要な費用を把握しておきましょう。
制度導入時に気をつけること
企業型確定拠出年金制度を運営するためには、「運営管理機関」と「資産管理機関」を設定する必要があります。
「運営管理機関」と「資産管理機関」は、従業員の情報や資産の管理などを含む、制度に関わる管理をする機関のことで、証券会社・保険会社・銀行などが委託先となります。
このふたつは企業が自由に選ぶことができるため、安定した運営を長期的に継続していくために、自社に合った機関を選定するようにしましょう。
運営管理機関とは
運営管理機関は、企業が導入する企業型確定拠出年金制度に関わる情報管理などを行い、企業と従業員をサポートする専門機関です。
運営管理機関となるためには、厚生労働大臣及び内閣総理大臣の登録が必要であり、主に銀行・証券会社・保険会社などの金融機関がこれに該当します。
この機関では、加入者の個人情報の管理や運用の記録、資産運用の方法の選定や運用会社が提供する投資商品の提示を行います。
さらに、規約の作成や従業員に向けた導入前の説明会、機関によっては、導入後の投資教育などもサポートしてくれるでしょう。
また、運営管理機関が破綻した場合でも、加入者の年金資産は資産管理機関によって保護されていることにより、他の機関へ引き継がれるため、年金資産の安全性が確保されています。
【主な業務】
- 運用商品の選定・提示・情報提供など
- 加入者ごとの事務処理・運用記録・記録の管理など
- 加入者への導入前説明会・導入後の投資教育・相談窓口業務など
資産管理機関とは
資産管理機関は、年金資産の管理・保全を行う専門機関です。
企業型確定拠出年金の場合は、主に信託銀行が資産管理機関となり、依頼時には企業と資産管理機関において資産管理契約を締結します。
(個人の場合は、国民年金基金連合会が資産管理機関となります。)
従業員の大切な資産を預ける資産管理機関は、信頼性と運用実績に基づいて慎重に選定する必要があります。
【主な業務】
- 年金資金の保全管理
- 年金資金の記録管理
- 年金給付に関する情報管理
各管理機関選定時の確認事項
企業が企業型確定拠出年金を導入する際には、運営管理機関と資産管理機関の選定が非常に重要となります。
特に、選択する金融機関や制度設計によって必要な費用は大きく異なりますので、制度の運営に関わる費用の確認は念入りに行いましょう。
また、複数の企業がひとつの規約に加入する形態を取るのであれば、関連費用を比較的低く抑えることも可能です。
このように、企業がどのような制度を選ぶかによって、運営コストの見積もりは大きく変わります。
企業の経営者や制度担当者は、自身の会社にはどのような制度があっているのか、その制度を導入し継続して運営していくためには、具体的にどの金融機関が相応しいのかを熟考することが大切です。
その上で、選択する機関が提供するサービス内容とそれに伴う手数料を明確にすることで、より効果的かつ効率的な年金制度の導入が可能になります。
この全体のコストを把握し、継続的な運用に必要な投資を評価することが、企業にとって最も重要なステップのひとつといえるでしょう。
運営管理費用の例※
運営管理機関にかかる費用は、主に以下の3項目になります。
- 初期費用
- 経常費用/月額
- その他/都度
それぞれの詳細を確認していきましょう。
1.初期費用
制度の導入時や口座の開設時など、最初にかかる費用。
【導入一時金】
企業型DC導入時に支払われる一時金で、計画の立案や制度設計のためのコンサルティング料が含まれます。相場は数十万円程度が一般的です。
【口座開設手数料】
掛金を拠出するための口座を開設したり、申請書類の作成を行います。
加入者ひとりあたりに発生し、一般的に数千円程度です。
経常費用/月額
制度を運営している間、毎月必要となる費用です。
【事業主手数料】
企業が支払う運営管理費用は、月額で数万円から数十万円の範囲で設定されることが多いです。
【加入者手数料】
加入者ひとりあたりにかかる費用で、月額数百円から千円程度が相場です。
【収納代行手数料(振替手数料)】
掛金の収納業務に関わる手数料で、通常は月額数千円程度です。
その他/都度
企業型確定拠出年金においては、制度導入前の従業員への丁寧な説明や、導入後のフォローとして、継続的な投資教育が欠かせません。
また、従業員が離退職する際には資産移換が必要となります。
さらに、長期的に運営していく上で、必要に応じて規約を変更することも考えられるでしょう。
これらの事項が発生したときは、都度手数料や費用が必要となります。
【従業員説明会(導入前)】
制度の導入や変更時に開催する説明会の実施費用で、一回あたり数万円から数十万円です。
【投資教育(セミナーなど)】
加入者の投資意識向上を図るための教育費用で、一回あたり数万円程度が必要です。
【移換手数料】
他の運営管理機関への移換時に発生します。
一回あたり数千円の手数料がかかります。
【拠出休止事務手続き代】
掛金の拠出を休止する必要が生じた際に事務手続きが必要です。
【拠出再開事務手続き代】
休止した掛金の拠出を再開する場合に事務手続きが必要です。
【還付手数料】
加入者が退職などで資金を還付する際にかかる手数料で、ひとりあたり数千円です。
【規約等変更事務費】
制度の規約を変更する際に発生する手数料で、数万円程度かかります。
資産管理費用の一例※
資産管理機関にかかる費用は、主に以下の2項目になります。
- 資産管理手数料
- 資産管理手数料預託金
それぞれの詳細を確認していきましょう。
【資産管理手数料】
資産管理手数料は、年金資産の月末平均残高に応じて発生する手数料です。
これは資産管理機関によって定められるため、資産管理機関によって異なります。
一般的に、運用資産額の年率で0.055〜0.110%程度が相場とされていますが、資産残高の増加で逓減するため、料率については各資産管理機関に確認が必要です。
【資産管理手数料預託金】
資産管理手数料預託金は、 一部の資産管理機関が運用開始時に必要とする預託金で、企業の脱退や倒産等に備え、1年間分の資産管理手数料を預託金(無利息)として預け入れるものです。
この金額は、資産管理機関や運用プランによって異なります。
| 資産残高区分 | 料率/年 |
| 5億円以下の部分 | 0.110% |
| 5億円超10億円以下の部分 | 0.099% |
| 10億円超20億円以下の部分 | 0.088% |
| 20億円超50億円以下の部分 | 0.077% |
| 50億円超100億円以下の部分 | 0.066% |
| 100億円超の部分 | 0.055% |
※ 本記事でご紹介した各種手数料や手続きの名称は、各運営管理機関例・資産管理機関で異なります。
制度導入には時間に余裕を持って
企業が企業型確定拠出年金を導入する際、費用以外にも、準備期間として多くの手続きを行う時間が必要となることを留意しておきましょう。
この制度の導入は、単に財務的な側面を評価するだけではなく、長期的かつ戦略的な計画に基づく判断が求められます。
まず、企業は、制度の導入と運営に適切な運営管理機関と資産管理機関を選定するために市場調査を行い、複数の候補から最適な専門機関を選びます。
また、従業員に向けた導入前の説明会や、継続的な投資教育計画と実施も、導入プロセスとして重要な項目といえるでしょう。
そして、制度の根幹となる制度設計には、従業員のニーズや企業の財務状況を考慮した計画が必要となりますが、調整を行い、労使の合意を得ながら準備を進めていくのは非常に手間がかかります。
しかし、企業はこれらのプロセスを丁寧に行うことで、長期的に安定した企業型確定拠出年金の基盤を築くことができます。
したがって、導入を決定する前には、これらの時間が必要なプロセスを熟考し、時間に余裕を持って、計画的に進めることが大切です。
可能であれば、制度のシミュレーションだけでなく、導入前の費用なども想定した「導入におけるシミュレーション」もおこなってみるとよいでしょう。
これらを企業内ですべて完結させるのは非常に難しいため、導入前のサポートから導入後のアフターフォローまでを一貫して行ってくれる運営管理機関を選び、アドバイスを受けながら準備を進めていくのがおすすめです。
制度導入には諸費用と期間時間を含めて熟考を
企業型確定拠出年金制度の導入は、企業にとって重要な決断となること、そして導入には諸費用と準備期間が必要であることを留意しておかなければなりません。
長期にわたるコミットメントが求められるこの制度は、ただ導入するだけでなく、企業が安定して運用するための基盤作りと、従業員に対しても継続的な管理とフォローアップが不可欠です。
より利用しやすい制度作りをするためには、制度導入前後の準備や制度運営には専門的な知識が必要となるため、導入からアフターフォローまでを一貫して担ってくれる「運営管理機関」を選定し、専門家からのアドバイスを受けることをおすすめします。
また、従業員の資産を管理する「資産管理機関」も財務負担や従業員の資産運用の効果に大きな影響を与えるので、慎重に選定してください。
こうした専門家のサポートを受けながら制度を構築していくことで、企業は従業員に対して価値ある福利厚生を提供するとともに、企業自身の財務を適切に管理し、負担を軽減することが可能となるでしょう。
企業型確定拠出年金は、適切に設計され、管理されることでその真価を発揮します。そのためにも、費用と時間をかけて制度について熟考し、計画的に制度導入を進めることが求められます。


