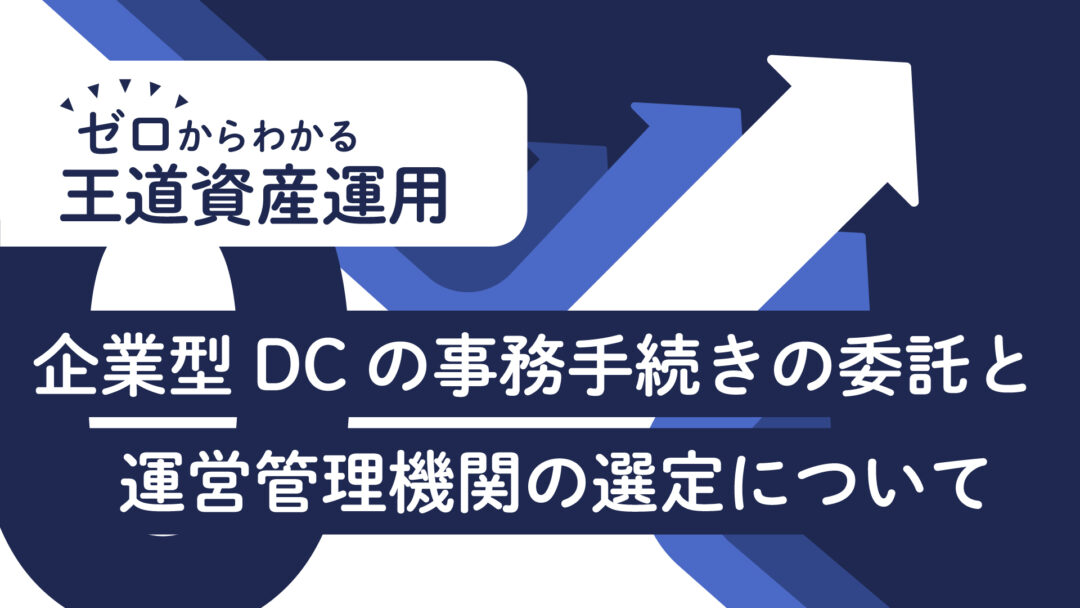
企業型確定拠出年金の事務手続きを委託するメリットとデメリットとは?運営管理機関選定のポイントも解説
企業型確定拠出年金を導入する際は、制度の設立・運営・管理の準備が必要です。
そのためには、企業内に担当部署を設けたり、制度に詳しい担当者を任命する必要がありますが、これには事務負担が発生します。
担当者は、自社の制度や企業型確定拠出年金に関わる法律について豊富な知識を持ち、常に最新の情報を把握しておく必要があり、制度への加入や脱退において様々な手続きを行うことが想定されます。
今回は、「実際にどのような事務負担が発生するのか」や、事務委託をする場合のメリットやデメリットなどを解説していきます。
企業の制度担当者様は、ぜひお役立てください。
企業型確定拠出年金制度を導入したら事務負担が発生する
企業型確定拠出年金は、企業が毎月決まった掛金を拠出し、従業員が自身で資産を運用する仕組みの私的年金です。
従業員は自分で運用商品を選択し資産を運用しますが、その運用結果によって将来の受取額が変動するため、適切な商品選択と運用を行う必要があります。
この企業型確定拠出年金制度を導入・運営する場合、企業は運営管理業務の全部または一部を行うことができます。しかし、企業が全てを行うことは負担が大きいため、専門機関に運営管理業務の全部または一部を委託することが一般的です。
その場合は、「運営管理機関」を委託先として選定し、導入時に作成する年金規約に企業と運営管理機関がそれぞれどの運営管理業務を担うのかを明記する必要があります。
事務を委託するメリットは非常に多い
企業は、運営管理業務の全部または一部を、自社で行うこともできますし、制度導入時や導入後に発生する事務手続きを外部の運営管理機関に委託することも可能です。
まずは、制度の導入前後で想定される事務手続きを確認してみましょう。
企業型確定拠出年金制度に必要な事務手続きや業務の一覧
- 従業員への定期的な説明会の実施
- 従業員への継続的な投資教育の実施
- 従業員からの相談や問い合わせ対応
- 毎月の掛金に関する事務手続き
- 毎月の給与処理などの手続き
- 掛金額変更時の手続き
- 従業員が入社し、制度に加入する際の手続き
- 従業員が退職し、制度から脱退する際の手続き
- 従業員が資格喪失年齢を迎えたときの手続き
- 従業員の登録情報に変更がある場合の手続き
- 企業の情報に変更がある場合の手続き
基本的に上記のような事務手続きや業務が発生しますが、この全てを企業内で行うことは普段の業務を圧迫することが想定されます。
そのような事態を避けるためにも、専門知識を持つ外部の運営管理機関に委託する企業がほとんどです。
それでは、外部の運営管理機関に委託した場合のメリットを見てみましょう。
①専門的な知識のサポートを受けることができる
企業型確定拠出年金制度の運営には、年金制度はもちろん、投資や金融商品に関しての専門知識が必要です。
さらに、給与・年末調整・労務などに関わる知識やそれに関わる業務も必要となりますが、専門的知識を持つ運営管理機関に委託することで負担が減り、適切なサポートを受けることができます。
②各種手続きの負担減
企業型確定拠出年金制度を導入した場合、「企業型確定拠出年金制度に必要な事務手続きや業務の一覧」で列挙したような事務手続きが発生します。
毎月の掛金拠出に関する手続きだけでなく、従業員の入退社や結婚などによる氏名の変更などの従業員情報の変更の手続きも都度行うことになります。
従業員が多ければ多いほど増えることが想定される事務手続きは、運営管理機関に委託することで負担が軽減されます。
③最新の知識や法改正などの情報の提供
年金制度は、公的年金や私的年金に関わらず、法律や関連する情報が頻繁に更新されていきます。
企業型確定拠出年金やその他の確定拠出年金も、今後も法改正がされていく予定です。
制度の導入・運営・管理には、法改正や最新の情報を把握するだけでなく、従業員が適切に資産を運用できるように投資教育を行う必要もあります。
そのため、企業としては常に情報を最新のものにアップデートすることが求められますが、日々の業務をこなしながら知識を入れていくのは容易なことではありません。
このような観点からも、専門的知識を持つ運営管理機関に委託することは、安定した制度運営はもちろん、本来の業務遂行のためにも有効といえるでしょう。
専門家に委託するデメリットは「費用」
先述したように、専門的知識を有する運営管理機関への委託はメリットが非常に魅力的ですが、問題となるのがその「委託費用」ではないでしょうか。
事務手続きの委託にかかる「費用」やそれに伴う「手数料」は、削減できる費用と感じる場合もあるでしょう。
自社内で行える手続きや業務であれば、できるだけ費用をかけずに自社内で運営していきたいという気持ちと、制度運営に必要な専門的知識を備えてから導入したいという意識から、企業型確定拠出年金に興味はあるものの、なかなか導入に至れないという企業も多くあるようです。
しかし、企業型確定拠出年金制度を導入したあとの企業や従業員への税制優遇や福利厚生面、それらから得られる従業員の満足度や将来的な人材確保などを考えると、少しでも早い段階でスタートすることもメリットのひとつとなるといえるでしょう。
委託する業務や委託する運営管理機関によって費用や手数料は異なるため、企業内の予算や事務負担のバランスを検討し、具体的なシミュレーションをしてみるのがおすすめです。
事務委託先を選ぶ際は、以下のことに留意してみましょう。
運営管理機関を選ぶ際の3つのポイント
企業が企業型確定拠出年金制度を導入し、外部に委託する際、どの運営管理機関に委託するかは、しっかりと検討すべきポイントとなります。
その場合、基本として以下のことをチェックしてみてください。
①厚生労働大臣及び内閣総理大臣の登録を受けていること
確定拠出年金制度において、記録関連業務及び運用関連業務などの運営管理業務を行う専門機関は、厚生労働大臣及び内閣総理大臣の登録を受けています。
該当する企業は、厚生労働省が発表している「運営管理機関登録業者一覧」で確認することができます。
②軽減したい業務と依頼費用が見合っていること
先述しましたが、企業型確定拠出年金制度の導入には多くの事務手続きはもちろん、従業員への説明会や投資教育などを行う必要があります。
このような手間を考えると、外部への委託は有効的ですが、プランは会社によって様々となるため、個々の企業特有のニーズを満たしてくれるかは運営管理機関によりけりとなります。
そのため、委託する場合は、委託先が必要としている業務を担ってくれるのか、依頼費用が依頼内容に見合っているのかを見極める必要があるでしょう。
また、企業型確定拠出年金制度は、一度導入したら長期的に継続していくものになります。
委託費用やそれに関わる手数料なども、長期的に見て企業の予算にあっているのか、企業の財務を圧迫しないかなどのバランスを考えて検討しましょう。
このような観点からも、1社ではなく複数の運営管理機関に見積もり(シミュレーション)をしてもらうことがおすすめです。
③従業員の観点からもメリットが多いこと
外部の運営管理機関を探す際は、企業が負担する費用のことだけでなく、従業員にとってもメリットのある委託先であるかどうかも判断するようにしましょう。
企業型確定拠出年金は、企業は掛金を拠出するとはいえ、将来的に従業員が受け取る資産となります。
従業員ひとりひとりがより良い運用が行えるように、金融商品の選択肢が多いところや、従業員からの質問や対応に親身かつ的確に答えてくれるか、従業員への情報提供や投資教育をどれくらいの頻度で行ってくれるかなども検討材料にしてみてください。
運用管理機関は自社と従業員に合った選定を
企業型確定拠出年金の事務手続きを委託することには、複数のメリットとデメリットがあります。
メリットとしては、専門的な知識による運営管理が可能になり、企業の負担軽減が期待できたり、従業員に対する適切な情報提供や相談サポートが強化されることなどがあげられます。
一方で、デメリットとしては、外部委託費用やそれに伴う手数料が発生することや、企業特有のニーズに柔軟に対応できない可能性があげられます。
そのため、運営管理機関を選定する際は、費用だけでなく、サービスの質・運営実績・セキュリティ面などを総合的に評価し、企業のニーズに最も合致する機関を選ぶことが重要です。
企業と従業員双方にとって、制度に関してプロフェッショナルな知識を持つことはスムーズな制度運営と資産運用につながります。
最適な年金制度の運用をしていくために、複数の運営管理機関で見積もり(シミュレーション)をするなどして、委託先を選んでみましょう。


